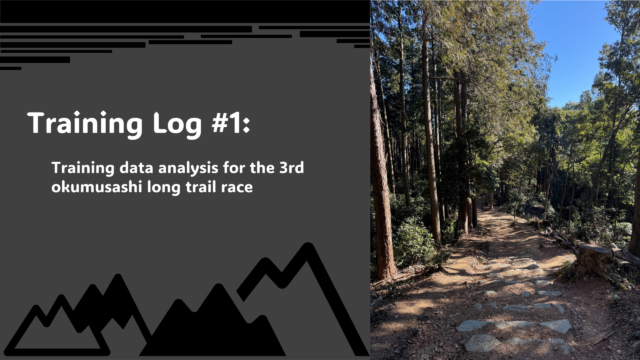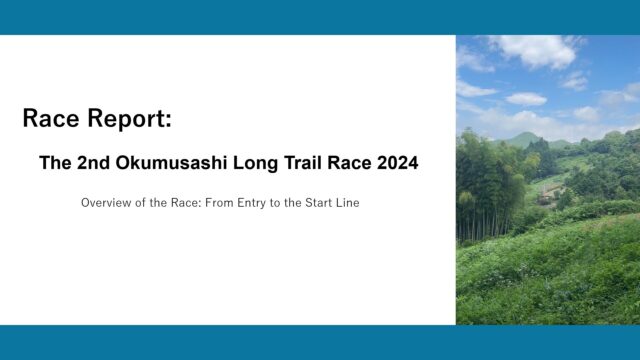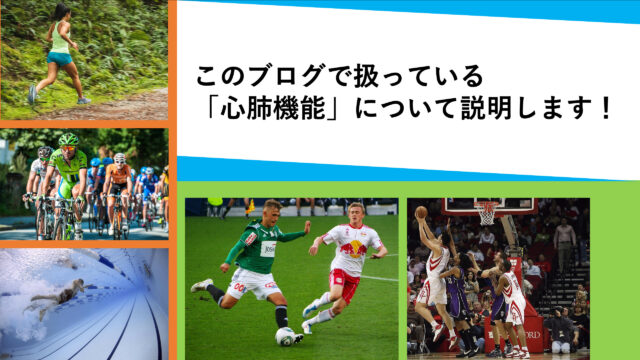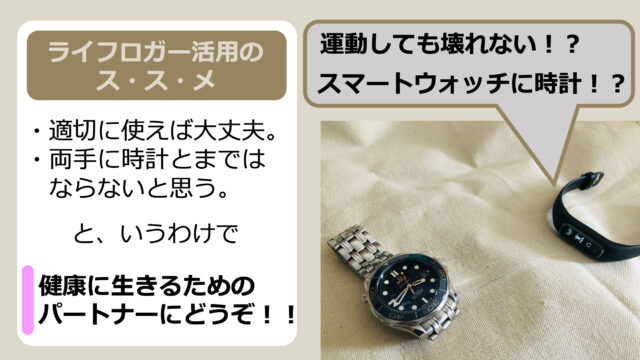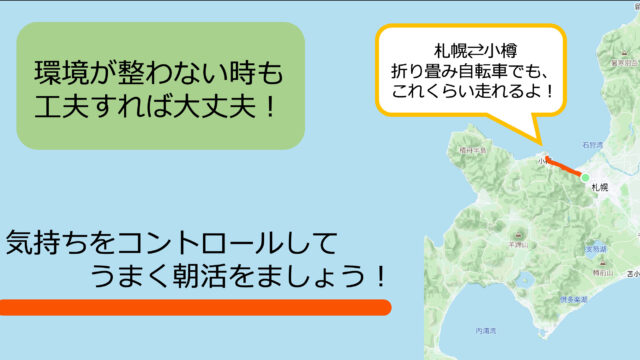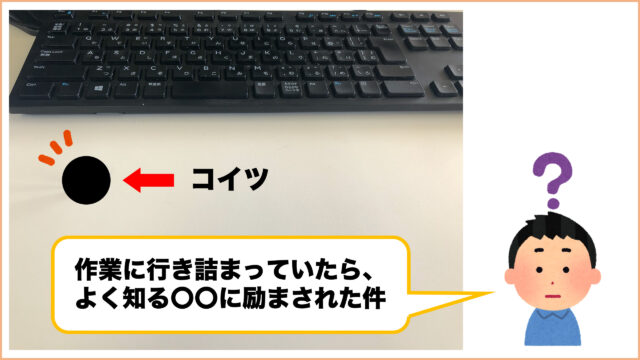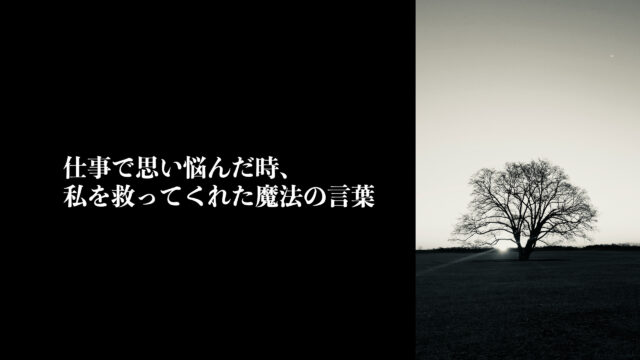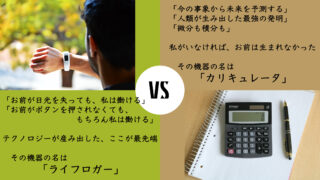生命維持に必要なエネルギーの量について
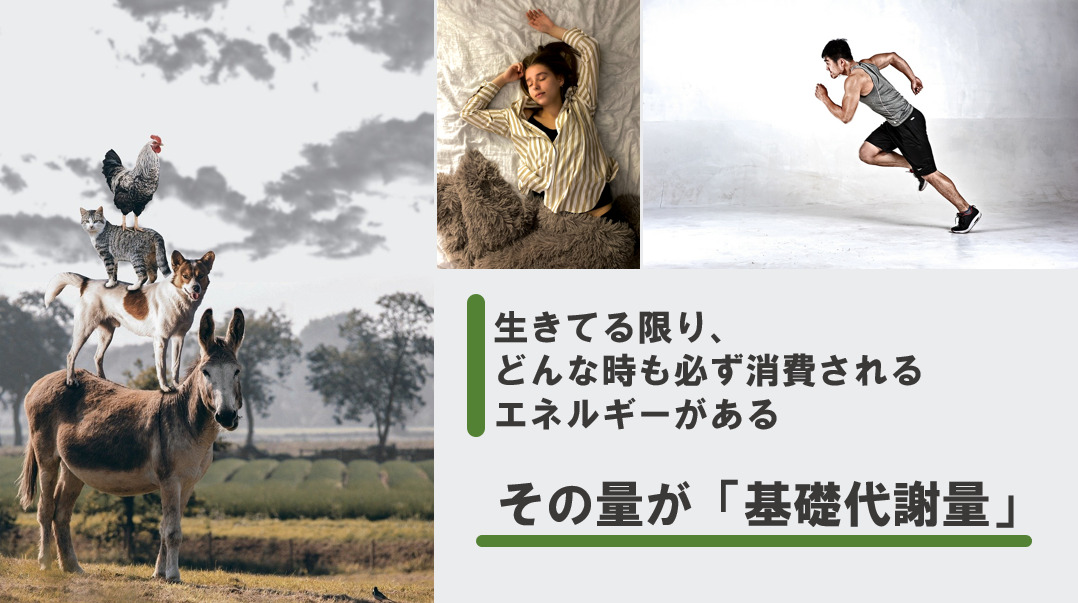
「ヒトは普段何もしなくてもエネルギーを消費する」
「運動してもエネルギーを消費する」
その両方がわかれば、1日に消費したエネルギーがわかるわけだ
運動をすれば、エネルギーは消費されます。
それだけではなく、何もしなくても消費されるエネルギーについてはご存じでしょうか。
今回はその、「何もしなくても消費されるエネルギー量」について、コトニクオリティーでざっくり解説したのちに、実際に皆さんの基礎代謝量を知っていただきたいと思います!
また少し、運動に関する理解が深まるとよいですね!
基礎代謝量について

ヒトの体を動かすエネルギー、何もしなくても、生命維持に必要なエネルギーが消費される
いつも漢字がいっぱい出てきますね。
キャッチコピーにも載せましたが、ヒトは、特に運動をしなくても生命の維持に必要なエネルギーを消費しています。
この、何もしなくても自然に消費されるエネルギーの量のことを、「基礎代謝量」と呼びます。
なんとなく分かっていただけたでしょうか。
実際に計算してみましょう

ここでは、実際に皆さんの基礎代謝量を計算する方法について紹介します。
ちなみに、ヒトの基礎代謝量は、人種によって若干の違いがあります。
平均的な身長や体重は国によって異なりますから、当然、日本独自のデータが必要になるわけです。
折角なので、日本の方々を対象とした方法を用いましょう!
本邦においては、国立健康・栄養研究所が基礎代謝量の推定式を発表してくれています。
エネルギー代謝研究室より転載
参考文献
“Ganpule AA, Tanaka S, Ishikawa-Takata K, Tabata I. Interindividual variability in sleeping metabolic rate in Japanese subjects. Eur J Clin Nutr 61(11): 1256-1261, 2007.”
“田中茂穂. 総論 エネルギー消費量とその測定法. 特集:必要エネルギー量の算出法と投与の実際. 静脈経腸栄養 24(5): 1013-1019, 2009. “
上記に大元のサイトを記載しましたが、こちらにも「国立健康・栄養研究所の式」を使用した計算フォームを用意しましたので、よろしければ使ってみてください。
いかがでしたでしょうか。
うまく計算されましたか?
これで、あなたの何もしなくても消費されるエネルギーの量が「キロ カロリー」という数値で大まかに明らかになりました。
大切なのは、皆さんの消費エネルギーはそれぞれ、大体このくらいなんだなという感覚をつかんでいただくことだと考えています。
自分の経験上は、推定値とはいえ結構妥当な数値を出してくれているように感じています。
みなさんの基礎代謝量を把握するには十分だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
運動時の消費エネルギーと合わせて考えてみましょう

これで、みなさんの何もしないでいて自然に消費されるエネルギーの量が明らかになりました。
これに、運動した(あるいは活動した)際に消費されたエネルギーの量を足し合わせると、一日に消費した合計のエネルギーの量が大まかに推定できる。
こういった理屈になるんですね。
では、実際に、一日に消費したエネルギーの量を、下の方法で計算してみましょう。
基礎代謝量:kcal(今回の記事から計算したエネルギーの量)
+
運動時に消費したエネルギーの量
二つの合計値が一日に消費したであろう大まかなエネルギーの量になります。
運動時に消費したエネルギーの量の計算方法は下記の記事で紹介していますので、ぜひお読みください。
これらの数値は、「年齢」や「体重」が加味されています。
つまり、年を重ねたり、運動によって体重が変化すると、代謝の量が変化するということです。
ですので、1~2週間ほどたったら、再度計算しなおしてみてくださいね。
エネルギー量を記録するときのポイント
- 基礎代謝や運動時のエネルギー消費量は、年齢や体重が関わっている。
- 定期的に計算をし直して、正しい数値に近い値を用いることが大切。
自分の体のことがわかるようになってくるって、なんだか楽しくなってきませんか?
蓄積が継続に繋がります。
「まずは、少しでも試してみてくださいね」
【小ネタ】一日に消費したエネルギーの量よりも、食べたもののエネルギー量が少なければ、、、

今回の記事を理解していただけた方は、もしかしたら、上記のような疑問が浮かぶのではないでしょうか?
だとすれば、皆さんはもうエネルギー代謝、運動、食事、この三つのバランスについて考える基礎ができた、と自信をもっていただいて結構だと思います。
「エネルギーの摂取と消費の関係という観点から言えば、その通りです!」
ですので、一日に消費したエネルギーの総量以上に食事をとらないようにしていけば、理論的には体脂肪量の減量につながるということになります。
実際には、栄養素(糖質、たんぱく質や脂質など)や運動の種類(有酸素運動の有無など)によって結果は変わってきますが、少なくとも私はこれだけの知識でも十分に運動と食事からみた健康管理ができると考えています。
これまで沢山の知識を世に出してくださった研究者のみなさんには本当に頭が下がります。
折角ですから、みなさんが健康な毎日を送れるように、活用させていただきましょう!